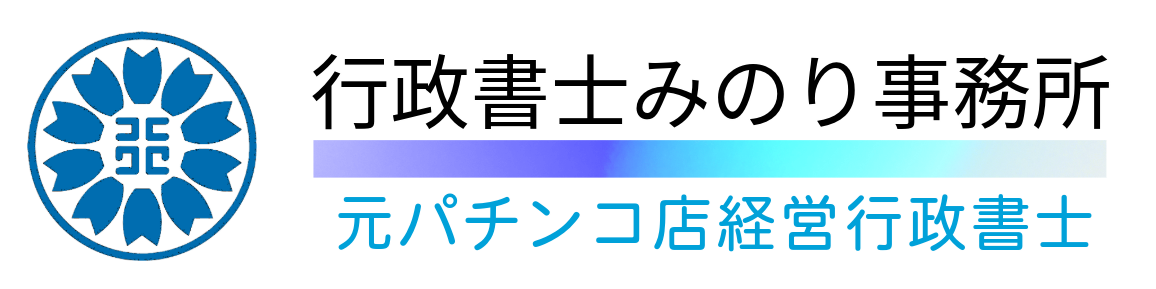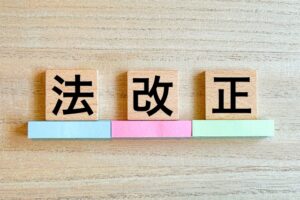古物商許可申請の必要書類と手続き完全ガイド【令和7年10月一部改正対応版】
今回は、古物商許可申請を考えている方々に向けて、必要な知識や手続きについて詳しく解説します。古物営業とは何か、どのように許可を取得するのか、また申請に必要な書類や注意点についても触れていきます。
特に、個人事業主やネット販売を行う方にとって、役立つ情報が満載です。これから古物営業を始めたい方は、ぜひ参考にしてください。
目次
古物商許可申請の基礎知識
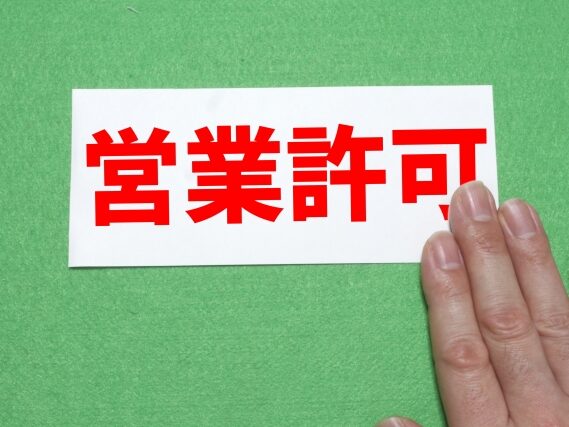
古物営業法の基本とその目的
古物の売買には、その流通過程において盗品等の犯罪被害品が混入する可能性があります。それを野放しにしておくと、結果として犯罪を助長することになるおそれがあります。そのため古物営業法では、法令等で定められた各種義務を果たすことにより、窃盗その他の犯罪の防止を図り、併せて被害が迅速に回復できる社会を維持していこうということを目的条文として掲げています。
古物とは?
「古物」とは「一度でも使用したもの」というイメージがあると思います。法では、それに追加して「使用されない物品で使用のために取引されたもの」「これらいずれかの物品に幾分の手入れ(修理など)をしたもの」といった3点を古物の定義としています。
古物の区分
古物(物品)は、13品目に分類されており、営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請(届出)することになります。ご自身が古物で取り扱おうとしている物品が、どの品目に該当するのかをチェックしておきましょう。
| 美術品類 | 書画、彫刻、工芸品等 |
|---|---|
| 衣類 | 和服類、洋服類、その他の衣料品 |
| 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等 |
| 自動車 | その部分品を含みます。 |
| 自動二輪車及び原動機付自転車 | これらの部分品を含みます。 |
| 自転車類 | その部分品を含みます。 |
| 写真機類 | 写真機、光学器等 |
| 事務機器類 | レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 |
| 機械工具類 | 電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 |
| 道具類 | 家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等 |
| 皮革・ゴム製品類 | カバン、靴等 |
| 書籍 | |
| 金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |
古物商許可申請の手続き

許可の要否と欠格事由の確認
まずは、ご自身がこれからやろうとしていることについて、許可が必要なのかをチェックしてみましょう。なお外国籍の方が許可を得ようとする場合には在留資格の制限が別にありますので注意ください。
許可が必要なケース
- 古物を買い取って売る営業
- 古物を買い取って修理等して売る営業
- 古物を買い取って使える部品等を売る営業
- 古物を買い取らないが、古物を販売するよう依頼を受けて、販売した後に手数料を貰う営業(委託売買)
- 古物を別の物と交換する営業
- 古物を買い取ってレンタルする営業
- 国内で買った古物を海外に輸出して売る営業
- これらをインターネット上で行う営業
許可が必要ないケース
- 自分の物を売る。(「自分の物」とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。)
- 自分で購入した物をオークションサイトに出品する。
- 無償で貰った物を売る。
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
- 自分で売った相手から売った物を買い戻す。
- 自分が海外で買ってきたものを売る。(「他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る」は含まれません。)
許可が必要なケースに該当していたでしょうか?該当していた場合は、続いての欠格事由にご自身と管理者候補、法人申請の場合は役員全員が該当していないかを確認しましょう。また、既に許可を受けている者が次に該当した場合は、許可の取り消しの対象となります。
※管理者とは
業務を適正に管理するための責任者として、必ず営業所ごとに1名管理者を選任しなければなりません。申請者が管理者を兼任することができますが、制限が掛かる場合があります。
古物商の欠格事由
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で、古物営業法施行規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条第1項の規定により、古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 古物営業法第24条第2項の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として古物営業法施行規則で定めるもの
- 営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のある者
- 法人の役員が前記1.から8.までに掲げる事項に該当するとき。
申請の流れと必要書類
- ①警察署への事前相談(電話)
- 古物商の許可申請は、主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課です。特に町村での申請の場合には、管轄する警察署を勘違いしてしまう場合もあるので、必ず確認しておきましょう。また所轄によっては追加の添付書類を求められることがあります。提出したときに言われて、何度も警察署まで行き来しなければならなくなるのは大変です。あらかじめ確認しておけば教えてもらえますので、こちらも欠かさずに行っておきましょう。
生活安全課の窓口受付時間は月曜~金曜(祝日・年末年始を除く)の
午前9:00~12:00まで。午後13:00~16:00まで。となっています。
・管轄の確認
・管理者の人選について
・必要な添付書類の確認(法定書類以外の書類が必要か)

- ②書類の作成
- 申請先の警察署と必要な書類が判明したので、書類を作成していきます。法定書類の一覧は下記のようになっています。
⑴申請書類
・古物商許可申請書 各1通
・別記様式第1号その1 (ア )
・別記様式第1号その1 (イ )
・別記様式第1号その2
・別記様式第1号その3 (法人の申請で2ヶ所以上の営業所において古物の取引をする場合に必要な書類)
・別記様式第1号その4 (実店舗をもたない非対面方式のネットショップなどの場合に必要な書類)
⑵添付書類(枚数等の詳細は後述します)
・定款及び登記事項証明書(法人のみ)
・略歴書
・住民票の写し(本籍又は国籍記載のもの)
・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
・身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの)
・URLの使用権限を疎明する書類(ホームページを利用して非対面で取引する場合に必要)
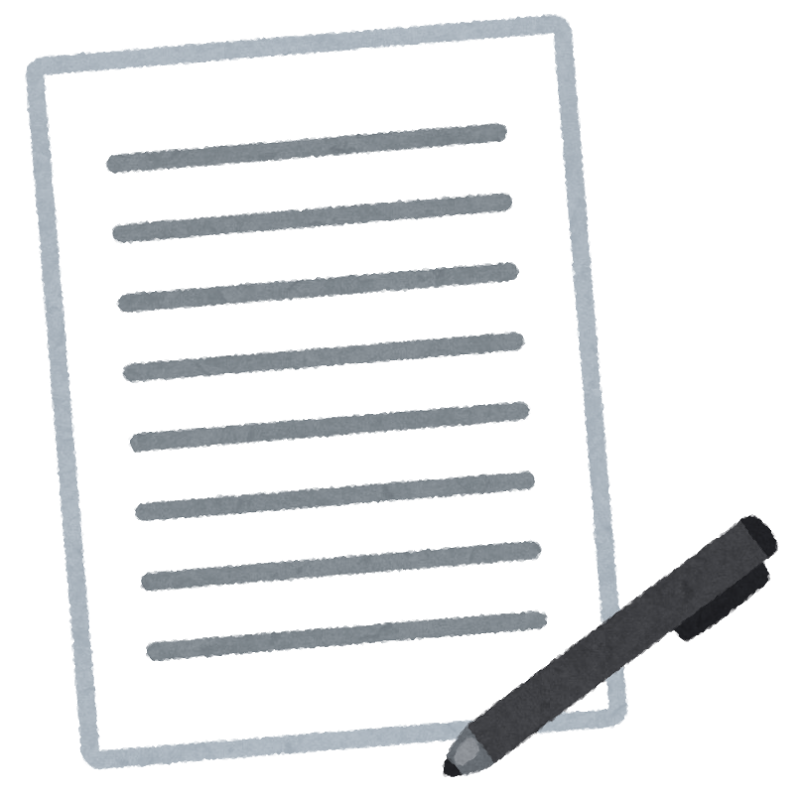
- ③警察署へ申請日の予約をして書類提出
- ①の事前相談の項にも書きましたが窓口受付時間は決まっています。申請書類の確認や手数料の納入など手続きに時間を要する場合が多いです。事前に警察署生活安全課へ申請日時の予約をしておいた方がスムーズです。
当日は、生活安全課窓口で書類の不備が無いかなどのチェックとともに、営業の中身を具体的に聞かれます。しっかりと説明できるように申請者本人が来署するようにして下さい。仮に行政書士に書類作成を依頼していたとしても、申請について弊所では帯同していただくことになります。
申請手数料は19,000円です。
手数料はキャッシュレス決済又は、現金の場合は愛知県収入証紙での納入になります。収入印紙は警察署内の各地区交通安全協会(運転免許を更新する部署)で販売していますので、当日の購入でも大丈夫です。申請の予約時間が遅めですと証紙売り場の営業時間を過ぎてしまうことが稀にあります。営業時間は予約の際に聞いておくなどしておきましょう。
※不許可となった場合及び申請を取り下げた場合でも手数料の返却はできません。

- ④許可証の交付
- 古物商の許可証は、申請から40日前後(遅れる場合もあります)で、申請場所の警察署において交付されます。受取りの際には警察から適正営業に関する説明等があります。遵守事項に係ることですので、申請者本人が受領に行くようにしましょう。
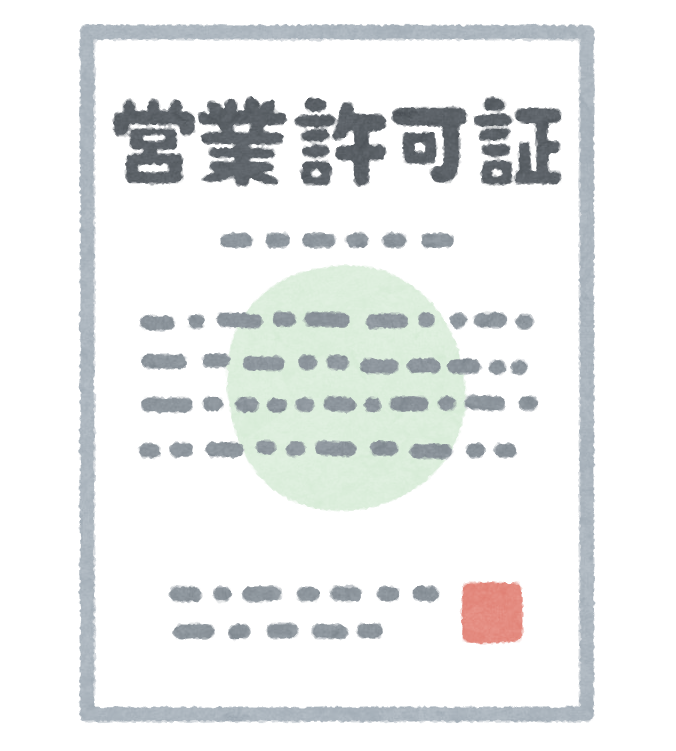
ここからは添付書類について表としました。よく勘違いされる場面は注意点として記載しておきますので、初めて申請される方はご覧ください。
| 個人申請 | 法人申請 | 管理者 | |
| 定款(原本証明が必要) 及び登記事項証明書 | × | ○ | × |
| 略歴書 (最近5年間の略歴を記載した書面) | ○ | 役員全員分 | ○ |
| 住民票の写し (本籍又は国籍記載のもの) | ○ | 役員全員分 | ○ |
| 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書 | ○ | 役員全員分 | ○ |
| 身分証明書 (本籍地の市区町村長が発行するもの) | ○ | 役員全員分 | ○ |
| URLの使用権限を疎明する書類 (URLの割り当てを受けた際の通知書の写し等) | HP利用 非対面取引の場合 | HP利用 非対面取引の場合 | ー |
◎注意点
- 添付書類の発行・作成日は、申請日から3カ月以内のものにしてください。
- 管轄する警察署によっては上記に記載されている書類以外の提出を求められることがあります。(例:賃貸借契約書や使用承諾書など)
- 定款の原本証明とは、確実に原本の写し(コピー)であることを申請者名義で証明することです。定款をコピーしたものの末尾に「以上、この写しは原本と相違ありません。令和〇年〇月〇日代表取締役【代表者氏名】」等と記載したものを用意してください。
- 住民票の写しとは「住民票のコピー」のことではありません。市区町村役場からもらった原本を提出してください。また許可証に旧姓を使用した氏名の記載を希望する方又は、外国籍を有する方で通称の記載を希望する場合、住民票に旧姓又は通称が記載されている必要があります。
- 身分証明書とは、破産宣告または破産手続開始決定の決定通知を受けていない等の証明書のことです。市区町村役場で発行できます。
- 個人事業者又は法人役員が管理者を兼任する場合は、誓約書以外の添付書類は省略できます。その場合の誓約書については個人用と管理者用の2種類の誓約書を記載して提出してください。
- URLの使用権限を疎明する書類とは、プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からそのホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写し等です。
申請書類のダウンロード方法と記載例
各種申請書類は都道府県警察のホームページからダウンロードすることが出来ます(PDF形式とWord形式)。愛知県警の場合は県警トップページから
申請手続き→古物・質屋営業→古物商許可申請等
と進んでいただくと各種申請書類・届出書類・記載例・添付書類等が掲載されています。
古物営業法施行規則の一部改正と身分確認について
令和7年10月1日から取引金額に関わらず、古物商が買受けを行う際の身分確認及び帳簿に記載をしなければいけない古物が追加されます。
改正箇所
改正前
・自動二輪車及び言動付自転車
・ゲームソフト
・CD、DVD、ブルーレイディスク等
・書籍
改正後は上記に加えて、
・電線
・金属製のグレーチング(いわゆる側溝の蓋)
・エアコン室外機
・電機温水器機のヒートポンプ
以上が追加されます。
これら古物は万引きや盗難を経由しての売買を規制するための品目です。改正後は昨今の金属類の大型盗難事案に対応するための屋外金属製品が追加されることになります。1万円未満であっても買受けをする際は、身分確認と帳簿の記載をお忘れなく!
身分確認の方法
住所、氏名、生年月日等が確認事項となります。運転免許証やマイナンバーカード等で身分確認を行ってください。
許可後の手続き
古物営業は「全国1許可制」となっています。それにより複数の店舗をもつ事業者さんは、事前事後の届出(変更届出書)を届出ができる警察署が主たる営業所を管轄する警察署でなくとも可能です。書換えを伴わない変更事項については、現況の届出事項にある全ての関係警察署で届出ができるようになっています。下記にまとめましたので、ご覧ください。
◎主たる営業所を管轄する警察署でしか受理できないもの
| ①新規の許可申請 ②書換申請 ③返納理由書 ④再交付 |
◎事前の届出(変更日の3日前まで)
| 変更内容 | 主たる営業所又はその営業所の移転、新設、廃止、名称変更 |
| 受理可能な警察署 | 現況届出事項にある全ての関係警察署で可能 |
| 対象となる営業所 | 全ての営業所(県内外問わず可能) |
◎事後の届出(変更後の14日以内まで。法人登記が必要な者は20日以内)
| 受理可能な警察署 | 対象となる営業所 | 変更内容 |
|---|---|---|
| 主たる営業所を 管轄する警察署 | 主たる営業所 | 書換を伴う変更事項 法人・個人の名称変更、所在地変更、法人代表者変更、代表者氏名・住所変更 |
| 現況届出事項にある 全ての関係警察署 | 全ての営業所 (県内外問わず) | 書換を伴わない変更事項 管理者交代、管理者氏名・住所変更等 法人役員追加・削除・氏名・住所変更 取扱区分の変更、HPの追加・削除 |
おわりに
ここまで古物商の営業許可に絞って解説してきました。古物営業は他にも古物市場主、古物競りあっせん業の許可申請。仮設店舗、競り売りの届出等があり奥が深いです。
売る気があるなら許可をとった方がよいとも言われる古物商ですが、賃貸借物件などでは添付書類が増える傾向がありますので事前の相談が断然にお薦めです。
行政書士みのり事務所では、警察行政の生活安全課に係る許可・届出を専門としています。古物商に限らず、風営法に関連した許可・届出についてもお気軽にご相談ください。お問合せお待ちしております。
電話でのお問い合わせ052-265-5390受付時間 10:00-20:00 [ 土日祝除く ]
メールでのお問い合わせ お問い合わせには2営業日以内にご返答差し上げます投稿者プロフィール

最新の投稿
 お役立ちコラム2025年12月11日警察行政手続きのオンライン申請対象が拡大!その注意点と利用のメリット
お役立ちコラム2025年12月11日警察行政手続きのオンライン申請対象が拡大!その注意点と利用のメリット お役立ちコラム2025年11月11日新法・金属盗対策法①!金属くず買受業の届出のポイント解説
お役立ちコラム2025年11月11日新法・金属盗対策法①!金属くず買受業の届出のポイント解説 お役立ちコラム2025年10月30日改正風営法の実務!追加された添付書類と「密接な関係を有する法人」とは?
お役立ちコラム2025年10月30日改正風営法の実務!追加された添付書類と「密接な関係を有する法人」とは?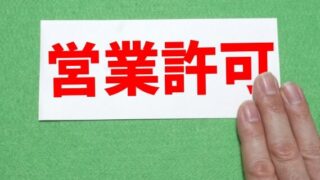 お役立ちコラム2025年9月18日古物商許可申請の必要書類と手続き完全ガイド【令和7年10月一部改正対応版】
お役立ちコラム2025年9月18日古物商許可申請の必要書類と手続き完全ガイド【令和7年10月一部改正対応版】