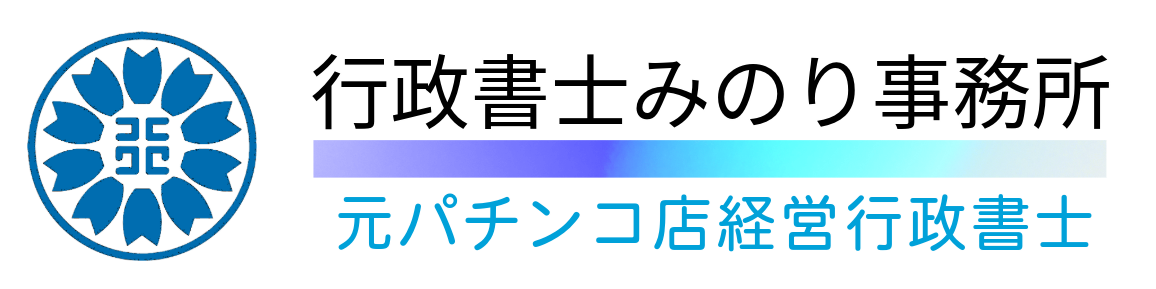改正風営法施行によせて
はじめに
※この記事は主に風営法1号営業について記載しています
改正風営法が令和7年6月28日に施行されました。
私も前職のパチンコ業(風営法4号営業)で、過去に広告規制を始めとする様々な通達・通知を経験してきました。現場では営業についての方針、注意喚起など大変な状況であろうことと思います。施行後の動きについてですが、主にホストクラブの営業方法や広告の規制についての報道や情報が多いように思われます(執筆時R7.7月上旬)。繁華街を歩いていても黒塗りされた看板やアドトラックが目立ちますね。
その一方、これまでは飲食店として「飲食店営業許可」を取得して営業してきた、スナックやコンカフェ、ガールズバーなどはどうなっていくでしょう?
スナック、コンカフェ、ガールズバーなど業態を指す名称は重要な判断材料にはなりません。必ず押さえておかなければならないこと。それは営業の実体として〈接待〉を伴う飲食または〈遊興〉を行っているかどうか。という点です。
これに当てはまる営業を許可を得ずに営んだ場合には、無許可営業にあたります。この規制は改正風営法以前から、変更されることなく今日まで続いています。しかし、今回の改正風営法では無許可営業に対する〈罰則〉が以下のように強化されました。
- 風俗営業の無許可営業に対する罰則の強化(2年以下⇒5年以下の拘禁刑、200万円以下⇒1千万円以下の罰金)
- 両罰規定1に係る法人罰則の強化(200万円以下⇒3億円以下の罰金)
先ほども述べたように、無許可営業の罰則は以前から存在していました。またその罰則の量定も風営法のなかでは最も重い部類に入ります。しかし、今改正にともない警察行政による指導や取り締まりの強化は免れないこととなると思われます。
お店の代表様、オーナー様に限らず管理者様。ご自身のお店が無許可で〈接待〉を行っていないか?今一度、ご自身の目で営業時間中のチェックをなされてはいかがでしょうか?
ご自身のお店が〈接待〉にあたるのか?風営法の許可を申請したほうがいいのか迷っている。そのような場合、まずは風営法を専門としている行政書士に相談してみてはいかがでしょうか?
ここからは、許可申請についてなるべく簡潔に触れていきますが、風俗営業許可までの道のりは、長く険しいものです。しかも既存のお店からの許可申請となると、調べてみたら要件をみたしていない。または、満たせない。ということも十分に考えられます。弊所でなくとも、かまいません。まずは最寄りの専門行政書士に相談することで「継続可能な営業」の道を模索していきましょう。
今すぐに風俗営業許可はとれる?

風俗営業の許可申請から許可までに必要な審査期間ついて
飲食店営業許可申請と風俗営業許可申請では、申請に必要な時間、書類の分量、満たさなければならない要件などの難易度が格段に上がります。しかも申請までに必要書類の収集と作成に要する日数を加算して考えておかなければなりません。短期での取得は難しい許可営業となりますので、中期的な計画を立案して店舗運営の方向性を決めることも必要になります。
- 保健所に飲食店営業許可を申請して許可がおりる。(申請から約2週間程度)
- 公安委員会(警察署)に風俗営業許可を申請して許可がおりる。(申請から約55日程度)
ここまで申請に必要な期間について書いてきましたが、許可のために避けては通れない要件(条件)があります。それは三要件と呼称されるものです。
許可に必要な三要件とは

風俗営業に限らず、許認可や一部の届出には「満たさなければならない」とされる要件が定められています。満たしていない場合には許可をしてはならない。とされていますので、最も慎重な対応が求められます。全文を書きだすと、読む皆さんも大変ですから要点を簡潔にまとめてみます。
①人の要件〈欠格事由〉
- 破産者で復権していない
- 1年以上の拘禁刑または風営法4条1項2号に列挙する罪(公然わいせつ罪など)を犯して刑の執行を終えた日から5年を経過しない
- 暴力的不法行為をおそれがある
- アルコールを始めとする中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない
- 法人の役員などが上記の事項に該当する
②立地の要件〈制限地域〉
- 都市計画法上の用途地域による制限に該当しないか
- 条例などに規定する営業制限地域に該当しないか
- 保全対象施設(学校や病院など)からの距離制限に該当しないか
③設備の要件〈構造設備〉
- 客室の床面積を1室16.5㎡以上とすること(客室が1室のみの場合を除く)
- 外部からドアや窓などを通して見通せないものであること
- 客室の内部に見通しを妨げる衝立など(おおむね100㎝)を設置しないこと
- みだらな写真や広告物の掲示や表示をしないこと
- 個室がある場合には、その出入り口に施錠の設備を設けないこと
- 照度・騒音・振動の制限
以上の三要件を「全て満たしている」ことを客観的に確認することができるためには、言葉では足りません。書類や資料で明らかにする必要があります。もしも明らかにできなかった場合は許可されることはありません。風俗営業の許可は諦めて、飲食店営業の範囲内で既存店舗の営業を続けてゆく。ということになります。
飲食店営業をすでに営んでいる状態から、新たに風俗営業の許可をとろうとする場合に問題となる可能性が最も高いのが②立地の要件です。
①人的要件と③設備要件については、例えば管理者の人選を変える。設備工事で対応することで要件を満たすことは可能な場合があります。しかし、既に賃貸借契約を結び飲食店として営業を継続している。このような場合、至近距離に保全施設が存在していると許可はすることができないのです。
内装工事の発注をしてしまった。もう工事に入っている。というタイミングで立地要件を満たせないことが分かったら設備投資の資金もそれに費やした時間も諦めなくてはならなくなります。
最優先で行うべきは「制限対象地域2ではないか」と「営業所周辺の保全施設調査3」この2つを行ってください。
繰り返しになりますが、不明点やお悩みなど、ございましたら最寄りの風俗営業専門行政書士へご相談ください。
- 両罰規定とは、従業員が勝手に違法な行為を行ったとしても、その責任は法人にもおよぶ。ということです。 ↩︎
- 愛知県では第1種地域では許可ができません。その他の地域についても建築基準法等の制限を受ける場合があります。 ↩︎
- 営業所を中心とした半径100mの調査が必要です。 ↩︎
おわりに
行政書士みのり事務所では、次の3つに貢献しくことを理念としています。
- 安心で安全な街づくり
- 業界の健全化
- 順法精神に則る継続可能な営業
今回の改正に限らず、風俗営業とは時に無いものとして扱われるような場面に遭遇するばあいもあります。その業界に携わる事業者様を始め、管理者様、スタッフ様みなさんの伴走者として今後も活動していきます。
投稿者プロフィール

最新の投稿
 お役立ちコラム2025年12月11日警察行政手続きのオンライン申請対象が拡大!その注意点と利用のメリット
お役立ちコラム2025年12月11日警察行政手続きのオンライン申請対象が拡大!その注意点と利用のメリット お役立ちコラム2025年11月11日新法・金属盗対策法①!金属くず買受業の届出のポイント解説
お役立ちコラム2025年11月11日新法・金属盗対策法①!金属くず買受業の届出のポイント解説 お役立ちコラム2025年10月30日改正風営法の実務!追加された添付書類と「密接な関係を有する法人」とは?
お役立ちコラム2025年10月30日改正風営法の実務!追加された添付書類と「密接な関係を有する法人」とは?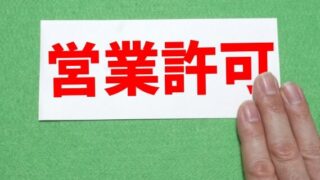 お役立ちコラム2025年9月18日古物商許可申請の必要書類と手続き完全ガイド【令和7年10月一部改正対応版】
お役立ちコラム2025年9月18日古物商許可申請の必要書類と手続き完全ガイド【令和7年10月一部改正対応版】